多摩川上流で東京の在来イワナを増やす
背景・ねらい
イワナは、渓流魚の中では一番上流に生息し、幻の渓流魚とも呼ばれています。東京都内では、イワナは、生息域が奥多摩の渓流の一部に限られ、生息数も少ない上、土砂崩れ等による環境の撹乱や、砂防ダム等の工作物による移動・繁殖の制限、遊漁による釣獲などによって、絶滅の危機に瀕しています。
一方で、イワナは、漁業権魚種として、毎年、数万尾の稚魚が内水面漁業協同組合から放流されています。しかし、稚魚を放流するためには、生きた魚を運ぶためのコストが必要ですし、また、山間部では、自動車の乗り入れが困難な場所も多いため、放流場所が限られてしまいます。
そこで、イワナを卵で放流すれば、持ち運びが容易になるので、より上流域に、効率よく放流場所を増やせます。また、稚魚まで育てるための経費・手間を削減できる上に、より河川環境に適応した魚が育ちます。東京都水産試験場では、このような観点から、東京都在来のイワナを守るために、イワナの発眼卵を渓流に放流し、増やす研究に取り組みました。
成果の内容・特徴
- 平成16年1月13日から14日に、放流用のステンレスカゴにイワナ発眼卵を入れて(図1)、多摩川上流域のA、B、C 3沢に3,000粒ずつ埋設放流しました(表1)。7月には、A沢は大雨のため、放流場所が土砂で埋まってしまいましたが、B、C沢は、地形に大きな変化はなく、放流カゴは無事でした。
- 同年8月から11月にB、C沢の放流場所付近で、電気ショッカー(直流400V)を用いてイワナを採捕しました(図2)。放流効果は、表1のとおりで、放流場所付近でのイワナの残存率が約0.3%から1.0%となり、発眼卵放流によりイワナが河川に定着することがわかりました。
- 今回放流したイワナの残存率は、先住イワナの密度が低い方が高い結果となりました(表1)。なお、放流卵由来のイワナは、耳石へのALC染色による標識で確認しました(図4)。
成果の活用と反映
発眼卵放流により、放流地点付近にイワナが残存することが確認されました。この方法を導入すれば、厳しい環境変化や人為的影響により分断・縮小されたイワナの生息範囲を広げることができます。そのことにより、東京都在来のイワナ資源をより安定的に維持できると期待できます。
ヤマメについては、毎年、ボランティア団体等の協同により発眼卵放流が行なわれています。イワナのについても、発眼卵放流が継続できる体制を作ることが今後の課題です。(木本 巧)
| 項目 | A沢 | B沢 | C沢 |
|---|---|---|---|
| 放流日 | 平成16年1月13日 | 平成16年1月13日 | 平成16年1月14日 |
| 放流卵数(個) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 採捕日 | - | 平成16年11月16日 から17日 |
平成16年8月2日 から3日 |
| 放流イワナ残存数(尾) | - | 31 | 10 |
| 放流イワナ残存率(%) | - | 1.03 | 0.33 |
| 全イワナ密度(尾/m2) | - | 0.15 | |
表1 平成16年度埋設放流結果
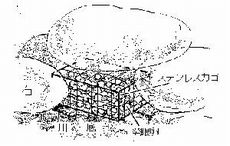 図1 イワナ発眼卵の放流方法 |
 図2 イワナの採捕方法 |
 図3 採捕したイワナ |
 図4 ALC染色により蛍光を発するイワナの耳石 |




