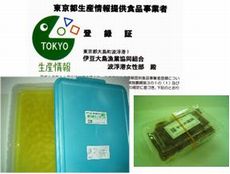地元と連携した加工品開発で地域振興に貢献
研究の背景とねらい
伊豆諸島の漁業は、離島という地理的な制約から、輸送コストに見合う高価格魚を主体とする漁業が営まれてきました。近年、輸入魚の増大や景気の低迷から、魚価安が続き、漁獲量も減少する中で、漁業経営は厳しくなっています。そこで、これまで利用価値の低かった水産物の活用方法を、地域の方々と連携して検討するとともに、魚食文化の普及を図り、漁業振興と地域社会への貢献を目的とする取組を行いました。
成果の内容と特徴
- 低・未利用資源を使ったすり身の作成
伊豆大島漁協女性部(以下、漁協女性部)で製造販売しているゴマサバ等の魚肉すり身について、製造指導、情報提供等を行いました。 - 漁業被害を与えるサメの有効利用
サメ一斉駆除で捕獲したサメ類の加工利用法について技術開発し、得られた成果を漁協女性部、学校給食センターへ情報提供しました。 - 「明日葉ところてん」の製品開発
大島事業所で製品開発した「明日葉ところてん」について、漁協女性部に技術指導(図2)、販売支援を行いました。 - 魚食の普及
大島町立波浮小学校へ、漁協女性部の取組みを紹介するとともに、課外授業に協力しました。 - 地産地消の推進
(有)御神火ファームより低脂肪乳(大島バター製造時の残牛乳)の利用方法について相談を受け、地元の食材を使った加工品の開発に取り組みました。
成果の活用と反映
一斉駆除で捕獲されたネズミザメが、漁協女性部で切り身に加工され、5月17日に大島町学校給食センターで「魚のマリネ」に調理されて学校給食(図1)に供されました。
「明日葉ところてん」の製造が始まり、大島町夏まつり、大島町体育祭体育レクリエーション大会、大島町農業祭、朝市などで販売される(図3)とともに、島内宿泊施設への販売も開始されました。また、11月6日と2月9日には、学校給食(図1)にも供されました。
漁協女性部の魚肉すり身、「明日葉ところてん」については、「生産情報提供食品事業者登録制度」に申請して登録を受けることができました(図4)。12月21日には、漁協女性部が波浮小学校の1年生から3年生を対象に、給食時間を利用して「魚の食べ方教室」を実施しました(図5)。低脂肪乳を使って牛乳寒の試作を行いました。
滝口 香穂
|
|
|
|
図1 学校給食。ネズミザメを使った「魚のマリネ」(左)と |
|
|
図2 明日葉ところてんの製造技術指導 |
図3 大島町夏祭りにおける明日葉ところてんの販売 |
|
図4 東京都生産情報提供食品事業者登録制度の |
図5 給食時間を利用した「魚の食べ方教室」 |