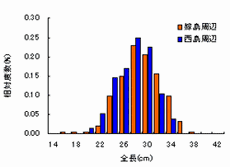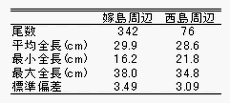小笠原の浅海漁業におけるアカハタ禁漁効果
背景・ねらい
小笠原諸島浅海域のアカハタは、近年の活魚出荷量の増加により資源の減少が懸念されている。地元漁業者は、平成10年3月より聟島列島嫁島周辺(距岸2km)に禁漁区を設定し、資源管理に取り組んでいる。嫁島浅海域の資源状況の調査と併せて自由漁業海域の西島周辺浅海域を対照区にして比較調査し、3年間の禁漁効果を評価した。
成果の内容・特徴
- 嫁島周辺(水深30m以浅)で実施した釣獲調査では、アカハタ338尾、シロダイ52尾、ナンヨウカイワリ28尾、その他20魚種115尾を採集した。
- 西島周辺(水深30m以浅)で実施した釣獲調査では、アカハタ76尾、シロダイ6尾、オジサン5尾、その他10魚種15尾を採集した(表1、図1)。
- 嫁島周辺に生息するアカハタは西島周辺よりも平均全長が1.3cm、最大全長が3.2cm大きかった(表2)。
- アカハタについてCPUE(単位努力量あたりの漁獲量:漁獲尾数/調査人数/時間)を比較すると、嫁島周辺が4.5、西島周辺が3.9で嫁島の方が有意に高かった。
- 嫁島周辺で採集した231尾の標識放流を行い、追跡調査で13尾を再捕した。調査海域のアカハタ資源量(釣獲サイズ)はピーセン法により1,998尾と推定された。
成果の活用と反映
本調査の結果をもとに、地元漁協と協力して嫁島禁漁区解禁後の管理方針を立てた。また、禁漁効果が確認されたことから、解禁後に新たな禁漁区を設けるとともに、将来的には、禁漁区の輪採制を導入することになった。
(文責: 山本貴道)
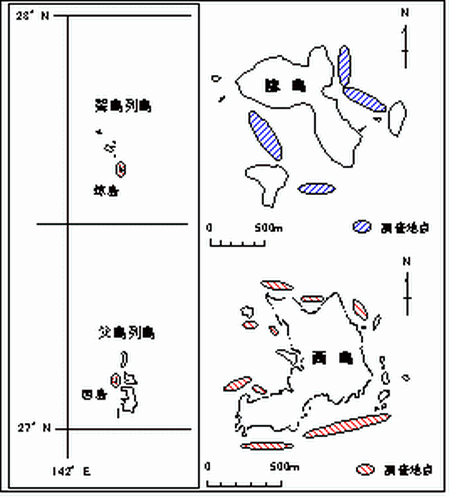
図1 嫁島と西島の調査地点
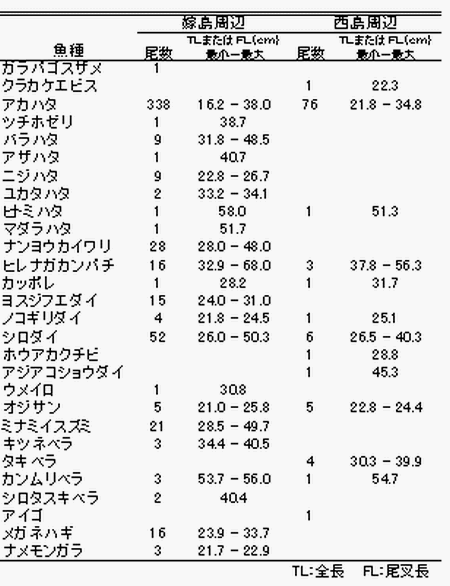
表1 漁獲された魚類
|
図2 アカハタ全長組成 |
表2 アカハタ測定結果 |
|
写真1 西島での調査風景 |
写真2 採捕された標識魚 |