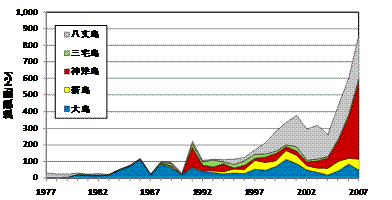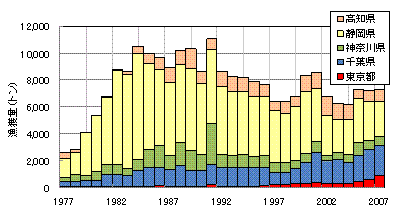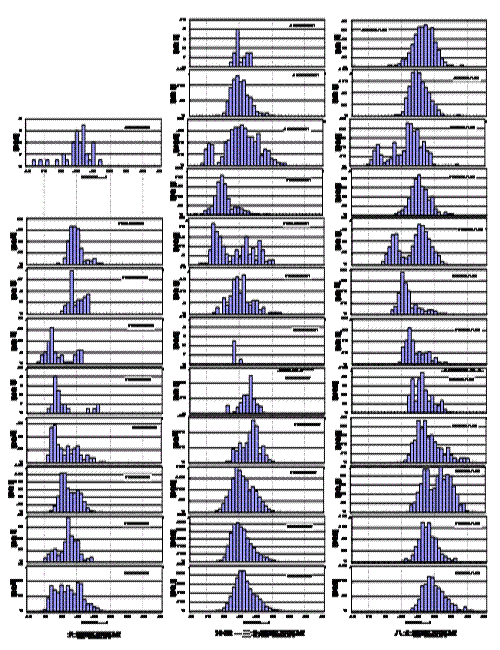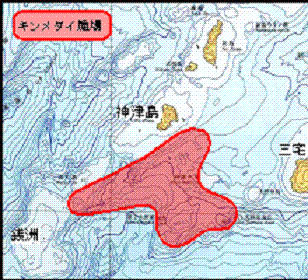キンメダイ資源動向調査 ~漁業者とともにキンメダイの漁場別資源状態を調べる~
キンメダイ資源動向調査
~漁業者とともにキンメダイの漁場別資源状態を調べる~
背景・ねらい
近年、東京都のキンメダイの漁獲量は増加し(図2、図3)、2006年には漁獲金額第1位になるなど、その重要性が増しています。キンメダイへの依存度が高くなるにつれ、将来にわたり資源を維持管理することが重要な課題になって来ました。このため、当センターでは、以前より行っていた漁獲情報の解析、島別魚体組成の把握などに加え、近年、神津島周辺において漁場別の魚体調査と漁業者操業日誌の解析を行い、資源管理の基礎としました。
成果の内容・特徴
① 伊豆諸島キンメダイ資源動態
伊豆諸島のキンメダイ漁獲量は現在高水準、CPUEはほぼ横ばい、魚体組成は大島地区では小型魚主体で近年も加入が認められるが、神津島~八丈島海区では近年大きな加入は認められていません(図4)。
② 漁場別魚体測定結果
2005年10月~09年2月の間に、24回、延べ419隻に漁場利用状況(図5)の聞き取りを行い、計8,971尾のキンメダイ魚体測定を行い、漁場別利用状況および漁場別体長特性を把握しました。利用頻度の高かった6漁場を比較したところ、2漁場で2006年から2007年にかけて、大型魚が減少する傾向がみられ、2007年から2008年にかけてはほとんどの漁場でやや大型化する傾向がみられました。
③ 漁業日誌解析結果
2006~08年に12隻の漁船から延べ2,449回の操業記録を入手し、漁場別利用状況、漁場別1日1隻当たりの漁獲量、漁場別の銘柄組成の推移を把握しました。2006年から2007年にかけて最も大型魚の多い漁場で、漁場利用頻度が減少する傾向が見られ、2007年以降小型魚の多い漁場の利用頻度が高まる傾向がみられました。
成果の活用と反映
この調査結果は東京都漁業者が行う伊豆諸島海域のキンメダイ資源管理方策策定の基礎となります。また、他県の調査による周辺海域のデータもあわせ、一都四県と国が協同して太平洋南部海域のキンメダイ資源の状態を把握し、同海域のキンメダイ資源の管理に活用されます。 (橋本 浩)
写真1 キンメダイ
図1 伊豆諸島におけるキンメダイ漁獲量の推移
(1977~2007年)
図2 一都四県キンメダイ漁獲量の推移
(「キンメダイ資源調査報告書」より)
図3 伊豆諸島海区別 尾叉長組成の推移
図4 神津島周辺キンメダイ漁場図