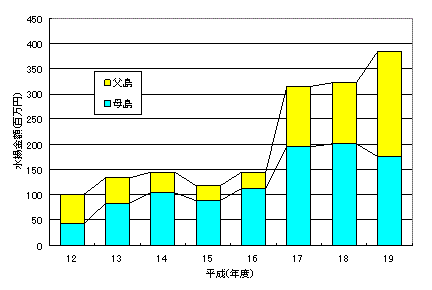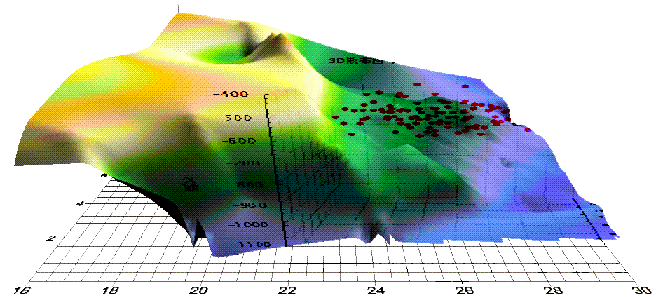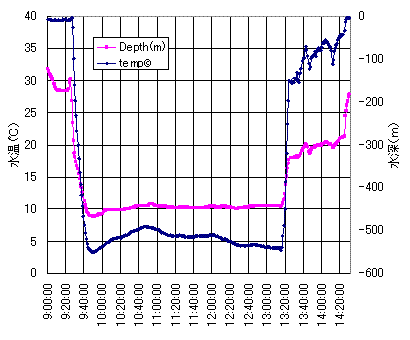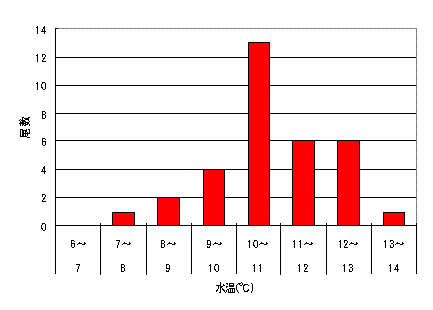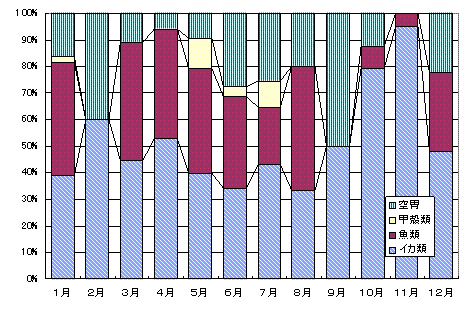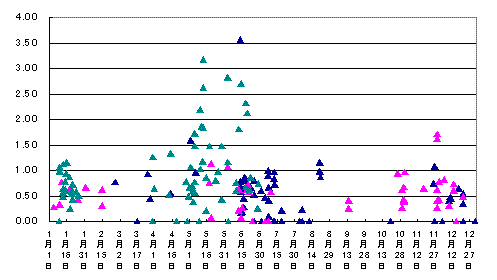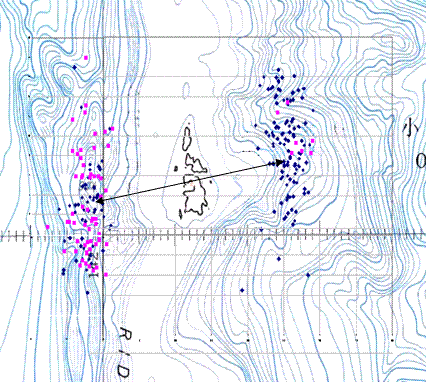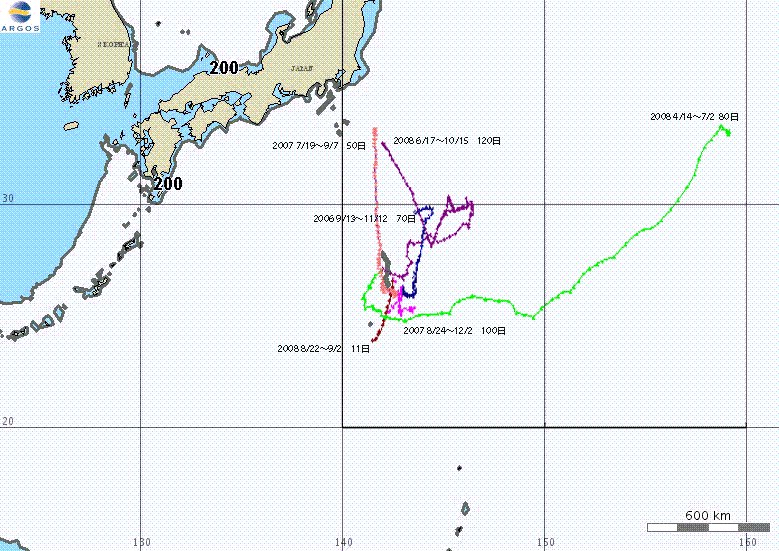どこで生まれて、どこへ行くのか 小笠原のメカジキ
どこで生まれて、どこへ行くのか 小笠原のメカジキ
背景・ねらい
小笠原では、沖縄から導入した「ソデイカ旗流し」漁を改良し、日中、深いところにいるカジキやマグロを対象とした「たて縄漁」が盛んに行われるようになりました。近年、水揚量も急増し、生産金額はメカジキだけで3億円を超えるようになりました(図1)。これは全水揚金額の約半分です。さらなる発展が望める一方で、漁業者からは、「いつか獲れなくなる日が来るのでは」という不安の声も聞きます。当センターでは、メカジキの生態の解明に向けて調査に取り組みました。
成果の内容・特徴
① 漁船からの聞き取り調査で、漁場は小笠原群島の東西10~20マイル沖の陸棚斜面で、海底の水深は800~1,500mのところにあります。父島東沖の釣獲位置を図2に示しました。また、漁具に付けた深度計の記録から、メガジキが針掛かりした水深は440~700mまでの広範囲に及びますが、その時の水温は10℃台が最も多いということが分かりました(図3)。
② 漁協に水揚げされたメカジキ272個体について、胃内容物を調べた結果(図4)、大部分はイカが占めていました。季節的には、アカイカの産卵時期(11、12月)には、特に割合が増加していました。魚類は、30~40%を占め、シマガツオ、タチモドキ、ミズウオ、ハダカイワシなど15種が確認されました。
③ 1年間の雌のKG値(生殖腺重量×10000÷尾叉長の3乗)の変化(図5)を見ると5月の中旬頃から6月中旬までの間、値が増加しています。また、6月には漁場が父島・母島ともに島の西側に移動することから、産卵場所は、小笠原群島の西沖ではないかと推察されます。産卵場を特定するために、引き続き調査を継続します。
④ 写真1のとおりPAT-tagを装着し7尾を放流しました。うち6尾よりデータが回収され、放流後の回遊経路が判明しました(図6)。大きく分けて北上する個体と南下する個体がありました。
⑤ 調査指導船「興洋」は海洋観測や調査の際、各水深の水温と同時に10℃台の水深を無線で操業中の漁船に情報提供しました。市場価値の向上を目指し、メカジキの身には脂質が多いことをPRするために、近赤外分光分析器を使った脂質の簡易測定技術を開発(写真2)しました。
⑥ 海面高度偏差図を参考に漁場形成場所を予測する取り組みも行なっています。さらに漁船に装備されている魚群探知機を活用し、DSL(プランクトン)層の反応から漁業者自身が漁場を探すことも提案しています。持続的な漁業を確保するために、漁業者に呼びかけ、小型魚の標識放流も始めました。
成果の活用と反映
漁業効率化のため、「興洋」では海洋観測の際、各水深の水温とともに釣獲数が多い10℃台の水深を無線で操業中の漁船に伝達するようにしました。また、海面高度偏差図を参考に漁場形成場所を予測する取り組みも行なっています。さらに、持続的再生産と長期的な回遊経路把握のために、漁業者に呼びかけ、小型魚の標識放流も始めました。(山口 邦久)
図1 メカジキの生産金額の推移
図2 父島東沖釣獲位置(赤丸)
図3 漁具の水深データ
図4 釣獲水温
図4 胃内容物の季節変化
図5 胃内容物の季節変化
図6 雌のKG値の推移
図7 漁場の移動
写真1 PAT-tagの装着
図8 放流後の回遊経路
写真2 近赤外分光分析器による脂質の計測