カツオの通り道を探す! カツオ曳縄漁場の海洋環境
カツオの通り道を探す! ~カツオ曳縄漁場の海洋環境~
【背景・ねらい】
八丈島のカツオ曳縄漁は、年間水揚金額の50%以上を占める重要な漁業です。しかし、近年、全国的な不漁傾向に同調し、八丈島でも水揚量が減少しています。また、燃料代等、操業コストの負担割合が高くなり、効率的な漁場探査が望まれています。
そこで、漁業調査指導船「たくなん」によりカツオ曳縄調査を実施し、カツオ漁獲位置での海洋観測結果からカツオの分布域における海洋環境特性について把握するとともに、航走距離当たりの漁獲量からカツオ曳縄漁の漁場評価を試みました。
【成果の内容・特徴】
1.八丈島でのカツオ曳縄漁における漁獲状況
八丈島における漁獲情報を解析した結果、操業船1隻当たりの漁獲量(CPUE)は、昭和55年(1980年)以降1隻当たり100kgから300kgで変動していましたが、平成18年(2006年)以降一隻当たり100kgを下回る低水準で継続していることが明らかになりました(図1)。
2.カツオ漁獲位置における海洋環境
1)カツオ漁獲位置の表層水温は、漁期初めの3月には水温18~20℃台、4月には水温18~21℃台、5月には20~22℃台となり、漁期後半になるにつれて、漁獲位置の水温が高くなる傾向が確認されました(図2)。
2)カツオ漁獲位置のクロロフィルa濃度の出現頻度は、0.15~0.2mg/m3と0.35~0.4mg/m3の2つのピークが確認され、全観測結果のクロロフィルa濃度の出現頻度とは明らかに異なることが確認されました(図3)。
3)カツオ漁獲位置の流向流速は、各年とも北向きの流れが確認されましたが、年によって、南東から東向きの流れで多く漁獲される傾向も確認されました(図4)。
4)平成17年に八丈島北東沖で形成された一隻当たり300~400kgを記録した好漁場周辺では、海洋観測結果から中層水温が周辺よりも低いことが確認されました(図5)。
3.航走距離当たり漁獲量による漁場評価
八丈島周辺海域において、緯度5分間隔、経度5分間隔の合計325区画を設定し、海区ごとの航走距離からの漁獲量を算出した結果、八丈島の北東10~20マイル沖にかけて、航走距離当たり漁獲量が高い海区が確認されました(図6)。
【成果の活用と反映】
今後、さらにカツオ曳縄漁での漁獲位置情報を集積することで、海区単位での漁場評価を進め、海洋観測結果と合わせることでカツオ漁場予測につなげていきます。 (堀井 善弘)
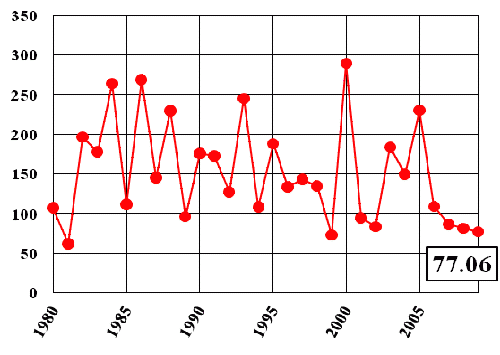
図1 八丈島における一隻当たりカツオ漁獲量(CPUE)の推移
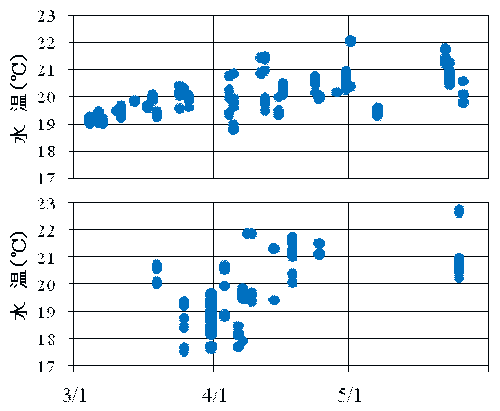
図2 八丈島周辺海域のカツオ漁獲位置における
表層水温の推移
(上段:2008年、下段:2009年)
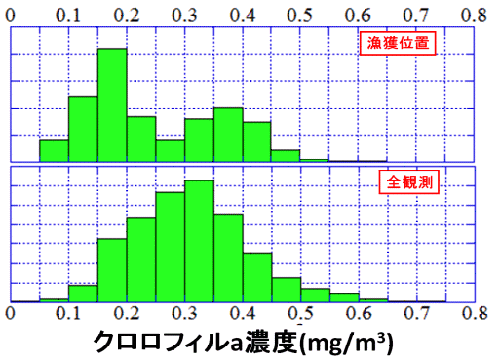
図3 八丈島周辺海域におけるクロロ
フィルa濃度のカツオ漁獲位置に
おける出現頻度(上段)と全調査
出現頻度(下段)
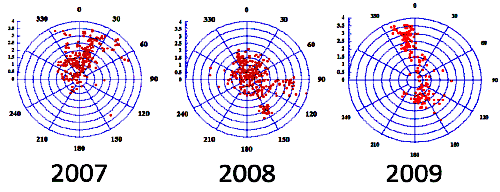
図4 八丈島周辺海域のカツオ漁獲位置における潮流の流向流速分布
(円周が方位、半径が流速を示す。)
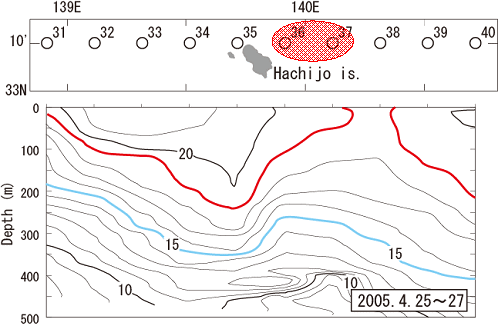
図5 2005年カツオ好漁場形成時における
鉛直水温分布
(赤丸部:1隻あたり300~500kg漁獲位置)
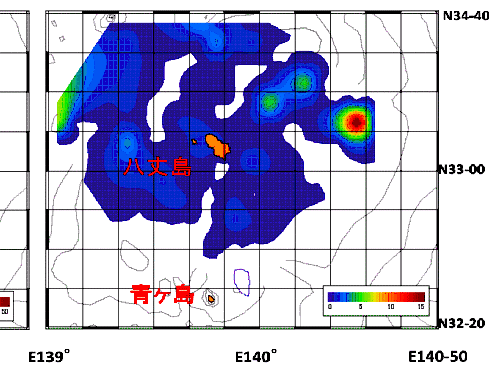
図6 調査指導船「たくなん」による八丈島周辺海域
における航走距離当たりカツオ漁獲量分布




