東京湾のマアナゴの成長と移動
背景・ねらい
東京内湾では、毎年200t前後のマアナゴが漁獲されており、アサリに次いで第2位を占める重要水産資源になっている。マアナゴの産卵場は、南西諸島の深海と言われており、産卵後ふ化した葉型仔魚は、黒潮に運ばれ、毎春、日本の沿岸水域にやってくる。
近年、資源の減少が指摘され、神奈川・千葉県では小型魚の保護などの資源管理が始まっている。そこで、都内湾における今後のマアナゴの資源管理に必要なデータを収集するために、定期的な漁獲物調査や底曳き網調査を実施し、月別の漁獲物の大きさ組成を明らかにし、内湾域における成長及び資源の添加・移動について検討した。
成果内容・特徴
- 1月には、年間の出現個体中最大個体を含む大型群と、270mmから469mmの中型群が認められた。2月、3月、5月には大型群は出現せず、中型魚群は月30mmの割合で成長している。
- 6月に羽田沖で126mmから257mmの小型魚4尾が出現した後、7月以降は小型魚が主体となった。この子形魚グループは、月10mmの割合で成長し、10月には約半数が270mm以上となった。
- 2月には、15号地水域でレプトケファルスを1尾採集した。また4月に全長600mmを超す個体を1尾採捕し、5月末には全長110mmに満たない稚アナゴを羽田沖で7尾得た。7月以降、中型魚群は、羽田沖漁場では採集されなくなった。
成果の活用と反映
市場価値のある全長350mm以上のアナゴを捕獲し、それ以下のメソアナゴを市場価値がでる大きさに育つまで漁獲しないで保護するためには、小型個体の多くなる7月以降の漁法を改善する必要がある。
|
1月に採補された年間最大長の個体 |
2月に、お台場で採補された |
|
活魚で流通するマアナゴ |
観測地点図 |
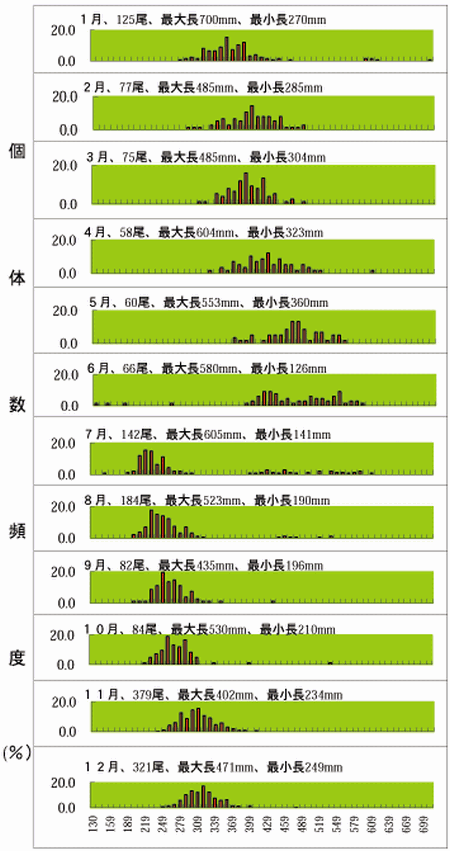
図1 1999年東京湾マアナゴの月別全長組成
| 階級 | 範囲(mm) | |
| 凡例 | 130 | 0から130 |
| 139 | 131から139 | |
| 149 | 140から149 | |
| ↓ | ||
| 709 | 700から709 | |








