内湾調査平成20年1月 マアナゴ体長組成の推移
マアナゴ体長組成の推移
マアナゴ(通称アナゴ)は天麩羅や寿司ネタで馴染みの深い魚ですが、東京湾奥の羽田付近でたくさん漁獲され、"江戸前のアナゴ"として評価が高いことは意 外に知られてないのではないでしょうか。本種は、ウナギのような丸い筒状の体型をしていて、体色は褐色、体側には頭部から尾部まで白い斑点が列をなしてい ます。その幼生(写真1、2)は、レプトセファルスleptocephalusと呼ばれ、日本より遙か南方の東シナ海や台湾方面などにルーツ(産卵場)が あり、海流に乗って冬春期に来遊すると言うのが有力な説です。
漁法は、無数の丸い穴があいた工事用の硬質塩ビパイプ(長さ約80㎝、直径10㎝)に、餌として主にカタクチイワシを入れて漁獲します(写真③)。餌につられて"返し"がついた入り口から入って筒の穴から逃げ出せなくなった個体が漁獲されることになります(写真4)。
図は平成19年1月~12月に羽田周辺の4地点で試験操業船(東京都内湾漁業環境整備協会が委託)により漁獲されたマアナゴの全長と数を表しています。
1月に漁獲された40㎝前後の個体は8~9月を除き12月まで認められます。一方、冬春期に来遊し初夏にかけて徐々に大きくなった個体が6月から漁獲される様子が見えます。なお、夏期を中心とした貧酸素水に覆われやすい時期に漁獲が一旦途絶え、その後10月以降、さらに成長して漁獲される様子が全長組成の動きからうかがえます。
|
写真1 東京湾奥で採集したマアナゴの幼生 |
写真2 同左の拡大画像 |
|
あなご船 |
マアナゴ |
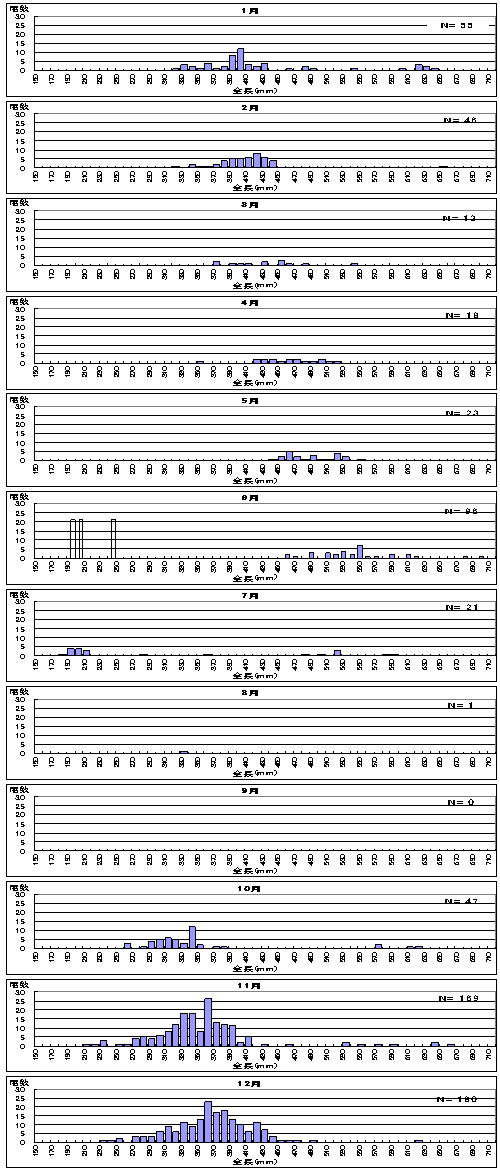
平成20年1月10日内湾水質調査結果
| 調査位置 | St.1 羽田洲 | St.2 羽田沖 | St.3 15号地 | St.4 三枚洲 | St.5 お台場 | |
| 時 刻 | 9:00 | 8:25 | 10:05 | 9:43 | 10:35 | |
| 天 候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 風向/風速(m/s) | N/3.0 | N/2.5 | NNE/1.5 | NNE/1.8 | N/1.0 | |
| 気 温 (℃) | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | 7.5 | |
| 実測水深(m) | 5.2 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 3.7 | |
| 透 明 度(m) | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | |
| 水 色 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | |
| (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | ||
| 水温(℃) | 表層 | 11.47 | 12.12 | 11.44 | 11.33 | 12.25 |
| 底層(B-1)m | 11.48 | 11.77 | 12.50 | 11.49 | 13.13 | |
| 塩分(PPT) | 表層 | 31.40 | 29.88 | 29.67 | 31.32 | 28.93 |
| 底層(B-1)m | 31.43 | 30.65 | 32.62 | 32.03 | 30.52 | |
| pH | 表層 | 7.66 | 7.58 | 7.59 | 7.66 | 7.48 |
| 底層(B-1)m | 7.62 | 7.60 | 7.60 | 7.66 | 7.52 | |
| DO(mg/L) (%) | 表層 | 8.25 | 6.54 | 7.10 | 7.83 | 6.59 |
| % | 92.2 | 73.7 | 78.3 | 87.2 | 73.5 | |
| 底層(B-1)m | 8.19 | 6.59 | 6.57 | 7.84 | 6.60 | |
| % | 91.5 | 73.7 | 76.3 | 87.9 | 76.0 | |
| 濁度(ppm) | 表層 | 4.1 | 4.4 | 6.0 | 3.3 | 4.4 |
| 底層(B-1)m | 5.1 | 6.1 | 18.5 | 2.8 | 3.5 | |
| 電気伝導率(mS/cm) | 表層 | 48.31 | 46.19 | 45.92 | 48.23 | 44.86 |
| 底層(B-1)m | 48.35 | 47.26 | 49.91 | 49.18 | 47.04 | |








