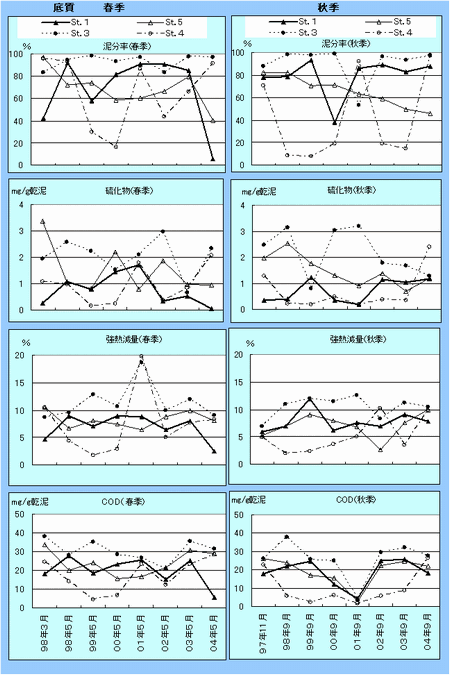内湾調査平成17年9月 多摩川河口域のマハゼ
平成17年9月 内湾調査
河口域のマハゼ
秋になると、水路や海浜公園で釣れるマハゼも12cmから15cmに成長します。多摩川河口の羽田空港誘導灯付近における底曳網調査でもマハゼが入りました。また付近では、マハゼ釣りの客を乗せた"釣り船"を見ることができました。
|
底曳網調査で採集したマハゼ(約12cm) |
誘導灯付近でのハゼの釣り船 |
内湾調査(曳網と低泥採取)
底質調査は、毎年5月と9月に行っています。平成16年秋までの分析結果を図に示しました。なお、1.泥分率は、0.063mm目合いの篩(ふるい)を通過した粒子の底泥全体に占める割合(%)、2.強熱減量は、泥の標本を数百℃氏の高熱で加熱した際に有機物が燃えることによる減量をそれぞれあらわしてています。
|
東京湾の5地点で毎月1回、網を海底に下ろして調査を行っています(お台場) |
エクマンバージ型採泥器による底質分析用の底泥採取(15×15cm) |
平成17年9月21日
| 調査位置 | st.1 羽田洲 | st.2 羽田沖 | st.3 15号地 | st.4 三枚洲 | st.5 お台場 | |
| 時刻 | 12:10 | 13:00 | 10:50 | 10:10 | 13:40 | |
| 天候 | c | c | c | b | c | |
| 風向/風力 | E/2 | E/4 | NE/1 | NNE/1 | E/1 | |
| 気温℃ | 28 | 28 | 27.5 | 28 | 28 | |
| 水深(B)m | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
| 透明度m | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | |
| 水色 | 10GY 3/2 dg-yG |
5GY 3/1 mg-YG |
2.5GY 3/4 vd-G |
10GY 3/2 dg-yG |
10GY 3/2 dg-yG |
|
| 水温℃ | 表層 | 26.0 | 26.2 | 25.3 | 25.8 | 25.6 |
| 低層(B-1)m | 26.0 | 26.2 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | |
| 塩分 | 表層 | 23.2 | 18.9 | 21.1 | 22.4 | 21.2 |
| 低層(B-1)m | 23.2 | 20.2 | 22.8 | 24.5 | 22.0 | |
| pH | 表層 | 8.29 | 8.74 | 7.90 | 8.28 | 8.30 |
| 低層(B-1)m | 8.30 | 8.61 | 8.16 | 8.33 | 8.04 | |
| DOmg/L | 表層 | 7.83 | 14.08 | 8.47 | 8.32 | 10.58 |
| 低層(B-1)m | 9.77 | 13.68 | 8.10 | 10.15 | 7.52 | |
| 濁度 | 表層 | 9.6 | 5.7 | 8.8 | 4.3 | 4.3 |
| 低層(B-1)m | 9.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 4.8 | |
| 電気伝導率 | 表層 | 3.63 | 3.03 | 3.38 | 3.64 | 3.35 |
| 低層(B-1)m | 3.69 | 3.21 | 3.60 | 3.82 | 3.48 | |
秋の河口干潟生物
多摩川河口の葦原(よしはら)や泥干潟で9月22日に生物観察を行いました。その結果、3月下旬の上陸時に全く姿を現さなかった生物にも動きがみられました。そのうち、アシハラガニとトビハゼの画像を掲載しました。これより岸沿いには、オサガニ(類)も多数見ることができましたが、5mから6mほど近づくと、一斉に生息孔に潜んでしまい画像に納めることはできませんでした。なお、2枚貝のヤマトシジミを除き、この場所で3月に優占したケフサイソガニは上記の種とは対照的に今回、見ることができませんでした。
|
写真1 流木とアシの奥に魚の死体が見えます。 |
写真2 近づくと、カニが魚から離れて流木の下に隠れました。 |
|
写真3 アップすると姿形がはっきりしてきました。 |
写真4 甲の特徴からアシハラガニとわかりました。 |
|
写真5 泥干潟では3cmから6cmのトビハゼを見ることができます。胸びれを器用に使って、跳ねるようにして葦原の茂みに素早く逃げ込みました。 |
写真6 水たまりの中に隠れたトビハゼ(唯一動きが鈍く撮影できた個体) |