内湾調査平成20年7月 お台場におけるアマモ移植試験概要
平成20年7月内湾調査結果
お台場におけるアマモ移植試験概要
平成16年以降、お台場海浜公園におけるアマモの株移植、苗移植、播種試験等の取り組内容を紹介してきましたが、今回、過去3年間に移植したアマモ株の消長や生育場に集まった生物をまとめてご報告します(写真1、2)。
さて、アマモの生育に必要な環境は、透明度が年平均2m以上、水温が5℃から30℃、塩分が17~34を満たす必要があると一般的に言われています。しかし、現在の東京都内湾では塩分条件はクリアできても、植物プランクトンが春以降に度々大増殖し、極端な時には透明度が数10㎝程になってしまい、その状態が1ヶ月以上続くことがあります。海岸沿いで、コーヒー色した海水を見て驚かれた経験の方もいらっしゃるかと思います(写真3,4)。
写真で見るように、透明度が数10㎝程の場合、潜水時の視界は想像以上に悪く、暗闇での手探り状態と同じようになります。アマモ株を計数する際、目印ライン代わりに2m程の長さの塩ビパイプを1m半ぐらいの間隔で何本も配置しますが、それでも株計数ができないことが何度かありました。
このように光が極端に遮(さえぎ)られてしまうと、アマモは光合成ができずに衰退します。特に、日射しが強く水温が上昇する夏場は、アマモの代謝が活発になる一方で光量不足に陥るために一気に衰退します。
さて、アマモの移植試験を開始した平成16年には、アマモの最適移植水深を探るため、アマモが干上がらないで生育できる基準海面-40㎝(大潮時に潮が最も引く0m水面を基準海面と呼ぶ)と、それより約20㎝ずつ深い同-60㎝、-80㎝付近で移植を試みました。その結果、春期にピークを迎えたアマモは、初夏以降、深場から順に消滅し、光量が得られやすい基準海面-40㎝付近が最も長期間生育できることがわかりました(図1)。
なお、富栄養化を通り越して過栄養化状態になった当該水域では、コンクリート護岸に普通に着生するフジツボ類やイガイ類の幼生密度が高まる夏場には、それらが葉体の周りを10日程で全て覆い尽くしてしまい、完全に光が遮断されてしまうこともありました(写真5)。また、アマモが生育しやすい透明度が良好な冬場であっても、葉体上を微細藻類が覆ってしまい、その重みで葉体がしなだれ砂に埋もれてしまうこともありました(写真6)。当該水域で試験して始めてわかる東京湾奥の厳しい現実です。
いずれにせよ、3年間に延べ7回程アマモを移植した結果を図2に一括して示しました。その結果、夏期の移植アマモは1~2ヶ月でほぼ消滅するのに対し、透明度が好転する晩秋の移植アマモは翌年の3~4月頃をピークに、その後徐々に衰退していき7~8月に消滅することがわかりました。
そして、生育期間中には、たった畳1~2枚分程に生育したアマモ場に砂泥底では通常見ることのできないワレカラ類が葉体から茎にかけて無数に群がる様子や、それらを捕食するメバル、スズキ、ギンポ類などの幼魚が遊泳する姿も観察でき、”アマモは稚魚のゆりかご”と言われるにふさわしい光景も見られました(写真7,8,9,10)。
今回、縦5m×横10m程の占用許可範囲で実施した小規模な移植試験ですが、アマモの生物蝟集(いしゅう=一ヶ所に集中して集まる様子)効果は大きいと判断されました。また、種をつくる花枝も形成されました。
現在、東京内湾(富津と観音崎を結んだ線上の内側)でアマモが自然繁茂している水域は、湾口に近く透明度の高い千葉県富津や木更津、神奈川県では走り水海岸です。しかし、東京湾奥の横浜市金沢区八景島近くの野島海岸で、平成15年に移植されたアマモが順調に生育し、海岸一帯に分布域を広げてアオリイカを始めとする様々な生物が集まることが報告されています。
今後、東京湾奥の東京都内湾でアマモが周年生育するためには、生育場となる砂泥地の確保は当然ですが、一定の光量が得られる透明度の高い生育環境が必要になります。
本来、栄養塩そのものは、様々な生物を育てる基礎生産物質として重要な物質ですが、流域人口が3,000万を越える東京都内湾では、栄養塩は再生処理水として、また出水時には未処理水が雨水とともに大量に流入するうえ、これまでに堆積した底泥からの溶出も加わり過栄養化状態になり、プランクトンの異常繁殖による透明度の低下を繰り返し招きます。
栄養塩の負荷を根本的に軽減する行政施策が急がれますが、”流しの水の一滴は川を経て海に繋がっている”ことを一人ひとりが常に意識しながら、環境に優しい生活を心がけていく習慣を身につけることも大切です。
|
写真1 お台場の人工干潟
|
写真2 移植後の様子 |
|
写真3 赤潮で焦げ茶色に一変。平成18年5月26日撮影 |
写真4 同左 |
|
写真5 フジツボ類やイガイ類で覆われた葉 平成18年8月11日に移植後12日目の状態 左は比較のため剥がした葉 |
写真6 葉体を覆う微細藻類。透明度の良い冬季に微細藻類が付着し、重さでしなだれる。平成18年1月8日撮影 |
|
写真7 畳2枚分繁茂したアマモ。平成17年6月6日撮影 |
写真8 草体の周りに集まるオオワレカラやヤドカリ類。平成18年6月3日撮影 |
|
写真9 集まったメバル幼魚
|
写真10 近づくと褐色化した葉体み尾びれを絡ませて隠れるギンポ類。中央やや上、丸い斑点が連続する。平成19年4月19日撮影 |
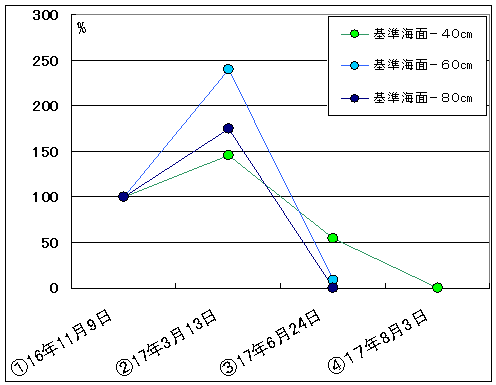
図1 アマモの深度別株数の推移。基準海面は大潮最干潮時の海面の高さ。移植時の株数を100%として表示ました。
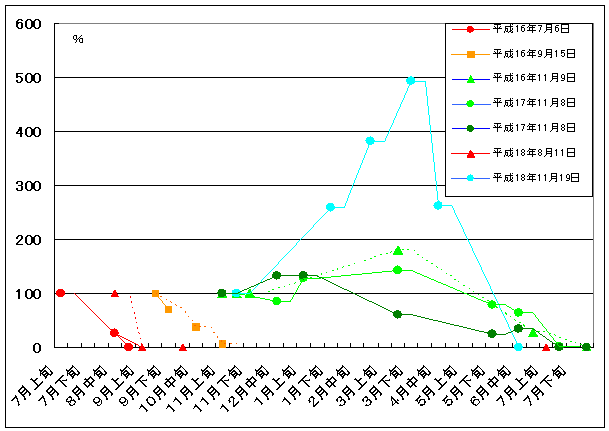
図2 平成16年以降に移植したアマモ株の年別、月別株数の推移。移植時の株数を100%として表示しました。
本年度のアマモの取り組みについて
アマモに関する新しい取り組みとして、野島海岸で6月20日に採集した花枝を占用許可水域へ試験的に設置しました(写真11,12)。また、7月4日の大潮時には、花枝から成熟して落下する種子が試験エリア外へ逸散しないように側面をプラスチックネットで囲い込む作業も行いました(写真13,14)。
本試験のねらいは将来、東京都内湾で規模の大きいアマモ移植を行った場合、それらが多年性アマモ(越年する)として生育できなくても、1年生アマモ(夏場に消滅し、種が冬期に発芽)として種子により増殖できるかどうかを判断する事前調査として行うものです。今の環境条件下で、冬期に発芽が見られることを期待したいものです。
なお、静岡県浜名湖では、透明度を始めとする環境条件が良好な場所で多年性アマモが、一方環境が厳しい場所では夏場にアマモが消滅し、その種子から発芽して世代を引き継ぐ1年生アマモが繁茂していることが報告されています。
|
写真11 アマモの花枝と種。平成20年6月20日撮影 |
写真12 アマモの花枝と種。上部左側に数粒の魚卵 |
|
写真13 プラスチックネットでの囲い込み作業。平成20年7月4日撮影 |
写真14 土嚢による固定作業
|
内湾で久しぶりに現れた生き物たち
内湾の5地点で行っている底曳網調査では、底層付近を遊泳するハゼ科魚類などの他、甲殻類、二枚貝など様々な生物が採集されます。
平成17年以降の2から3年間は、アサリ、サルボウ、トリガイばかりでなく、汚濁指標種として扱われているシズクガイ、チヨノハナガイ、そして最近ではそれらの死殻もほとんど採集されませんでした。しかし、本年6月以降、シズクガイとチヨノハナガイの生貝が荒川と旧江戸川に挟まれた三枚州や、荒川右岸側の若洲海浜公園沖で比較的まとまって採集されました(写真15)。汚濁指標種と決められた貝であっても、生貝として出現することは魚類などの捕食種の餌料として大切なことです。
また、羽田沖ではカタユウレイボヤが多く採集され、その中にエボヤ、シロボヤが幾つか混入していました(写真16,17)。当該水域で上記3種がまとまって採集されたのは珍しいことです。
いずれにせよ、肉食性巻き貝などの異常発生でない限り、様々な生物が常に生息できることが今の東京都内湾では必要です。
|
写真15 殻長10mm前後のチヨノハナガイとシズクガイ。平成20年7月17日撮影 |
写真16 カタユウレイボヤ
|
|
写真17 手のひら上の左がエボヤ、右の楕円状のものがシロボヤ |
平成20年7月17日内湾水質調査結果
| 調査位置 | St.1羽田州 | St.2羽田沖 | St.3 15号地 | St.4三枚州 | St.5 お台場 | |
| 時 刻 | 9:25 | 8:40 | 10:39 | 10:19 | 11:16 | |
| 天 候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | |
| 風向/風速 | (m/s) | S/1.5 | SE/2.6 | SE/1.8 | S/2.0 | SE/1.0 |
| 気 温 | (℃) | 30.5 | 30.3 | 31.2 | 32.8 | 32.5 |
| 実測水深 | (m) | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 2.5 | 3.4 |
| 透 明 度 | (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 水 色 | 10Y3/2 | 10YR2/2 | 10Y3/3 | 10Y4/3 | 5GY3/2 | |
| 水 温 | 表層 | 27.15 | 26.77 | 26.86 | 27.67 | 26.67 |
| (℃) | 低層(B-1)m | 24.93 | 22.70 | 25.15 | 25.91 | 24.77 |
| 塩 分 | 表層 | 20.7 | 18.9 | 18.9 | 12.2 | 19.4 |
| (‰) | 低層(B-1)m | 26.7 | 28.4 | 26.0 | 23.7 | 24.1 |
| pH | 表層 | 7.99 | 8.24 | 8.39 | 8.32 | 8.41 |
| 低層(B-1)m | 8.17 | 7.96 | 8.34 | 8.38 | 7.88 | |
| DO | 表層 | 5.88 | 12.36 | 10.28 | 8.85 | 14.23 |
| (mg/L) | 低層(B-1)m | 6.47 | 5.42 | 7.67 | 7.77 | 5.85 |
| 濁 度 | 表層 | 10.0 | 9.0 | 10.7 | 9.9 | 11.1 |
| (mg/L) | 低層(B-1)m | 8.5 | 1.8 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| 電気伝導率 | 表層 | 34.9 | 31.3 | 30.5 | 21.2 | 32.0 |
| (ms/cm) | 低層(B-1)m | 40.5 | 42.0 | 40.5 | 38.1 | 37.3 |





















