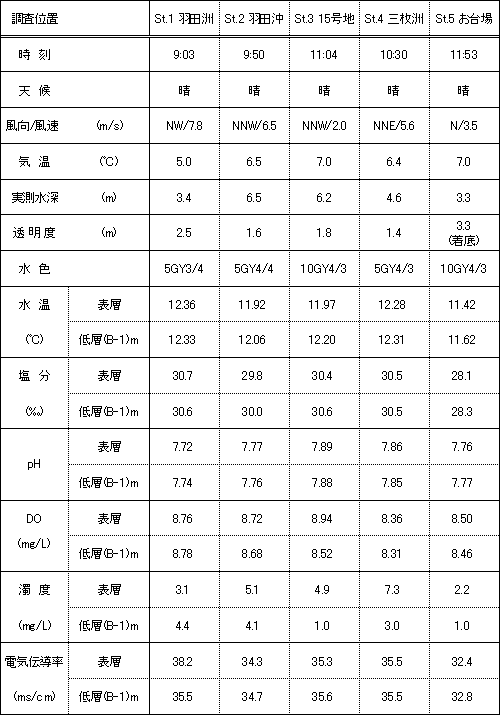内湾調査平成21年1月 羽田周辺のハゼ調査から見えてくる産卵期の雌雄行動の違い?
羽田周辺のハゼ調査から見えてくる産卵期の雌雄行動の違い?
“江戸前のハゼ"と呼ばれ、昭和30年代半ばまで漁業や遊漁の対象として人気の高かったマハゼの復活が東京湾再生のシンボルとして近年注目され、行政・NPO・住民・研究機関の協同によるハゼ釣り大会や研究会が開催されるようになりました。
このマハゼは、木々が紅葉する晩秋に河川下流や河口域等に集まりますが、冬春期における産卵準備のためと考えられます。今回、その産卵行動の一端を調査データを交えて紹介します。
図1は羽田周辺における過去20年間の延縄による月別・平均採捕数の推移を示していますが、秋には羽田周辺の浅場に集中し、産卵盛期の冬春期にはピーク時の約半数となっています。図2は平成18年10月から翌19年5月までの月別・雌雄別採捕数、図3は月別・雌雄比率を示しています。産卵盛期の1月以降、雄の採捕数が極端に減少することが前述の半減理由の一因になっているものと考えられます。それにしても雌雄組成の偏りは非常に興味深い現象です。
さて、マハゼは雄が砂泥底に産卵孔を掘り、雌を誘導して産卵させた後、雄が卵を管理すると言われますが、前述した雌雄組成の特徴はこれを支持するもので、冬春期の海底では雄が懸命に子育てに励んでいるのですね。

写真 マハゼの雌雄判別と成熟調査の様子
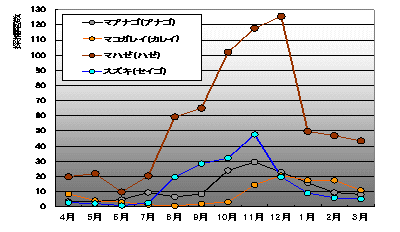
図1 羽田周辺の主要魚種月別・平均採捕尾数
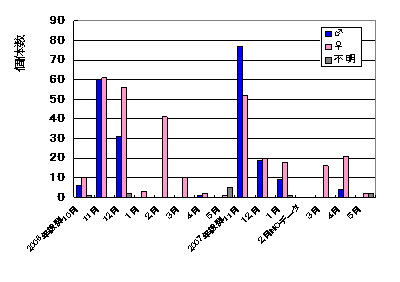
図2 マハゼの雌雄別・採捕数
注:東京都内湾環境整備協会報告資料を使用
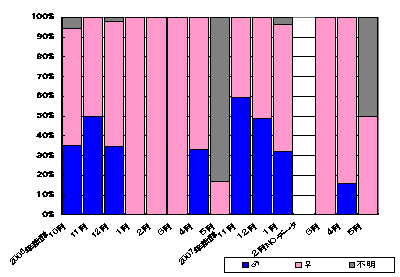
図3 マハゼの雌雄比率
平成21年1月15日内湾水質調査結果